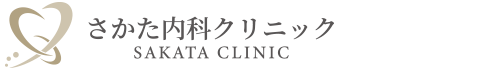心臓リハビリテーション

心臓リハビリテーション(心リハ)は、心臓病を患った方が再び安心して日常生活に戻り、再発を防ぐことを目的として、運動・食事・生活指導を通じてサポートする包括的なプログラムです。
当院では、循環器専門医とリハビリスタッフが連携し、一人ひとりに合わせた安全で効果的なリハビリを行っています。
当院では、循環器専門医とリハビリスタッフが連携し、一人ひとりに合わせた安全で効果的なリハビリを行っています。
なぜ必要か
心臓の病気には、狭心症・心筋梗塞・不整脈・弁膜症などがあり、いずれも心不全の原因となる可能性があります。
また、大動脈瘤・大動脈解離・閉塞性動脈硬化症などの血管疾患も、命に関わる重大な病気であり、専門的な治療が必要です。
心疾患は完治が難しく、病状を安定させて長く維持することが重要です。薬だけでは不十分な場合も多く、弱った心臓や血管とうまく付き合いながら生活する必要があります。
治療後の管理が不適切だと、再発・再入院・突然死のリスクが高まります。
心機能の低下により活動量が減ると、筋力や自律神経も衰え、生活の質(QOL)や精神面にも悪影響を及ぼします。加えて、動脈硬化の進行も大きな課題です。
また、大動脈瘤・大動脈解離・閉塞性動脈硬化症などの血管疾患も、命に関わる重大な病気であり、専門的な治療が必要です。
心疾患は完治が難しく、病状を安定させて長く維持することが重要です。薬だけでは不十分な場合も多く、弱った心臓や血管とうまく付き合いながら生活する必要があります。
治療後の管理が不適切だと、再発・再入院・突然死のリスクが高まります。
心機能の低下により活動量が減ると、筋力や自律神経も衰え、生活の質(QOL)や精神面にも悪影響を及ぼします。加えて、動脈硬化の進行も大きな課題です。
効果
下記のような効果があることが証明されています。
- 再発・再入院の予防
心筋梗塞や心不全などの再発・再入院リスクを大きく減らします。 - 体力・持久力の向上
運動療法により、心肺機能や筋力が改善し、日常生活が楽になります。 - 生活習慣の改善
食事、運動、禁煙などを見直すことで、病気の進行を防ぎます。 - 心理的な安定
不安や抑うつの軽減、気持ちの前向きな変化が期待できます。 - 生存率の向上
適切な心リハを行うことで、長期的な生存率が高まることが報告されています。 - 生活の質(QOL)の向上
自信を持って日常生活を送れるようになり、社会復帰もしやすくなります。
対象疾患
主に以下のような病気の方、手術後の方が対象になります。
- 狭心症の方
- 心筋梗塞発症後、治療を終え退院した方
- 慢性心不全で治療中の方(適応基準あり)
- 心臓の手術後の方
- 下肢閉塞性動脈硬化症で治療中の方
- 大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管手術後)で治療中の方
- 経カテーテル大動脈弁置換術後(TAVI後)の方
リハビリの内容
運動療法
心電図モニターによる監視と血圧測定で状態を確認しながら、自転車エルゴメーターを用いた有酸素運動および、レッドコードを使用したレジスタンストレーニングを実施します。運動処方に基づき、医師と理学療法士が運動強度を適切に調整し、安全に持久力の向上を図ります。

服薬・生活指導
看護師が中心となり、病気の管理や生活習慣についてお話を伺いながら、お一人お一人に合ったサポートを提供いたします。
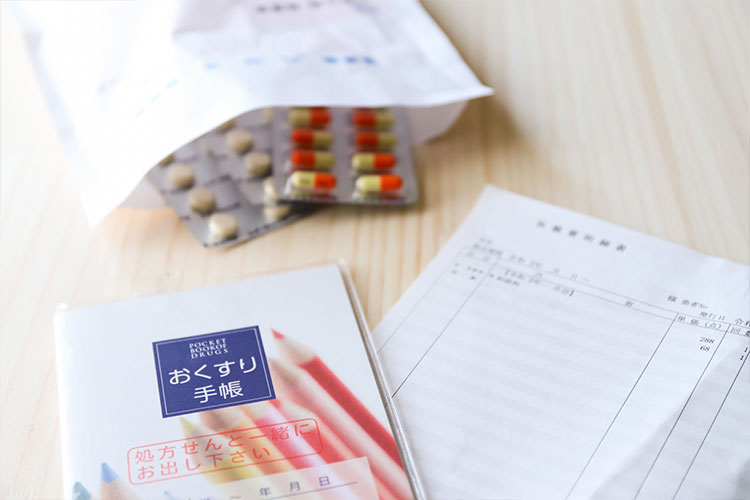
心理サポート
心臓病発症後の不安や抑うつに対するケアにも力を入れております。
“心リハ”は本来「心臓リハビリテーション」を指しますが、当クリニックでは“心(こころ)のリハビリ”という意味も込めて取り組んでいます。
“心リハ”は本来「心臓リハビリテーション」を指しますが、当クリニックでは“心(こころ)のリハビリ”という意味も込めて取り組んでいます。
実施までの流れ
医師による診察・リハビリ適応の確認
まずは、循環器専門医による診察を行い、心臓リハビリテーションを安全に実施できる状態かどうかを確認します。これまでの病歴や手術歴、現在の症状、服薬状況などを丁寧にお伺いし、必要に応じて心電図・血液検査・心エコー検査などを実施します。
そのうえで、リハビリの目的や期待される効果、注意点などについて、わかりやすくご説明します。
運動耐容能評価・運動処方作成
自転車エルゴメーターを使用できると判断した方には、心肺負荷試験(CPX)を受けていただき、その時点の体力(運動耐容能)を評価します。評価結果に基づき、適切な運動処方を行います。
個別プログラムの作成
評価結果をもとに、一人ひとりに合ったプログラムを作成します。心リハを続けるモチベーションにもつながるため、「何ができるようになりたいか」といった目標を患者さんと一緒に設定し、進め方を共有します。
また、「どの程度の運動をどのくらいの頻度で行うか」「食事で気をつけるポイント」「生活上の注意点」など、無理なく続けられる内容を提案します。
リハビリの開始
準備が整い次第、通院によるリハビリを開始します。運動療法は医師の指導のもと、心電図や血圧をモニターしながら、理学療法士や看護師と連携して安全に行います。また、運動療法に加えて、看護師による服薬や生活習慣のアドバイスも並行して行います。
通常は週1~2回から始め、体力の回復や状態に応じて運動量を調整していきます。
経過観察、継続サポートとスポーツジム提携
改善の程度を評価するうえで、患者さん自身の自覚症状はとても重要です。加えて、一定期間ごとに心肺運動負荷試験(CPX)を実施し、運動耐容能を再評価することで、回復状況を客観的に確認します。その結果をもとに、運動の強度や内容を見直しながら、無理のないペースで段階的にステップアップしていきます。通院リハビリ終了後も、ご家庭で継続できる運動メニューや生活管理の方法をご指導し、再発予防のサポートを継続します。また、必要に応じて定期的なフォローアップ外来や、スポーツジムとの提携による支援も行っています。
なお、心臓リハビリは開始から150日間、保険適用の対象ですが、病状や医師の判断により、150日を超えて継続することも可能です。